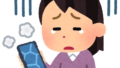こんにちは。山屋です。
お盆も過ぎたというのに暑すぎですね。早く秋が来てほしいものです。
さて、今回は「技術書」の読書術 達人が教える選び方・読み方・情報発信&共有のコツとテクニック という本を読みました。
技術書の選び方、効率的な読み方、より内容を定着させる方法等について書いてある本で、印象に残ったトピックを紹介させていただきます。
『3』の発想
本に限らず『3』の発想が大切であるという話があるそうです。2つではその間の関係しか見えないが、3つならば発想がその先に広がっていくとのことです。これを技術書の選び方に適用すると、以下の読み方ができそうです。
入門書、専門書、逆引きの3通り読む
入門書から学習を始めて専門書を読んでさらに知識を深めるだけでなく、学校の勉強で使っていたようにドリルなどがあればより知識を定着させることができます。ドリルに対応する本として、目的から実現方法を紹介する本である「逆引き」が挙げられます。
この3種類の本を読めば実務で使えるレベルになるでしょう、とのことです。
入門書を3冊見比べる
同じ難易度のを複数見比べるというのも1つの方法だそうです。
3冊ともに同じことが書いてあった場合、それはとても重要な部分であるとわかります。逆に1冊にしか書かれていなかった場合、そこまで重要ではない知識であったり、新しい技術であったりするかもしれません。
比較することで知識の重要度を知ることができます。
時間制限読書法
定めた時間内に1冊を読了することを目標とする読書法です。最初は90分に設定し、慣れてきたら短くしていくと良いでしょう。この方法には以下のメリットがあります。
集中して読書できる
この時間だけ、と決めれば周囲の誘惑にも負けず集中して読める可能性が高まるでしょう。加えてパーキンソンの法則(人間は与えられた時間を全て使ってしまう傾向がある)によって、制限時間内に終わらせようという意識が働きやすくなるようです。
悪書のリスクを軽減できる
たとえ自分に合わない本を読んでしまったとしても、90分の損失だけで済みます。素直に最初から読んで、後半になってから自分にあまり必要な本ではないと判明すると時間の無駄ですね。(私は最近これをやらかしてしまい、とてもがっかりしました)
成長のチャンスはアウトプットにあり
学んだことをアウトプットすることが成長に繋がります。
理由の一つとして、もしも本の内容を誤って理解してしまった場合に気づくことができるというものが挙げられます。(学校の勉強でも練習問題やテストがないと間違いに気づけませんよね)
アウトプットの例は以下です。
コミュニティに参加する
他のエンジニアと議論できるだけでなく、人脈を広げることができるというメリットがあります。会社の中では出会えないようなスキルを持っている人とも関われるかもしれないので刺激になるでしょう。
LTに挑戦する
コミュニティや勉強会で、5分程度のLT(Lighting Talk)会が開催されていることがあるので、参加してみるのも良いでしょう。
カンファレンス等に登壇する場合は準備が大変だと思いますが、5分ならば比較的気軽に話せるでしょう。自分がどんなことを勉強しているのか、興味を持っているのかといったことを発信すると周囲の人からアドバイスをもらえるかもしれません。
また、5分程度のLTといえども資料の準備は必要です。そのときにどうやったら相手にわかりやすく伝えられるのかと、話す順番等を考えることになります。ある内容について話す際に前提知識も説明しなければいけないということに気づくでしょう。考える中で、自分の中では当たり前のことであっても他の人にとってはそうではないことや、自分の知識の抜けや漏れに気づくといったことがあると思います。これを繰り返すことでより理解が深まるのです。
ブログに書く
発表するのはハードルが高いと感じる場合におすすめの方法です。
発表資料を作るときのように知識の整理ができますし、記録として残るというメリットがあります。
私もこの項目を読んだので、今まさにブログを書いているというわけです。ブログを書くにあたって、今の自分に特に有用な項目は何だろう?自分はこの本に何を求めているのだろう?と考えながら読み返して、より有益な情報が得られたと感じています。
感想
エンジニアとして生きていく上では避けられない「技術書」をより良く読める方法について知ることができて良かったです。
私は「技術書を読む速度を上げたい」「技術書の理解度を高めたい」というモチベーションでこの本を手に取りました。その観点で印象に残ったことを今回ブログとしてアウトプットしました。
私が今回紹介したのは本のごく一部で、他にも「本の選び方」「1年で1,000冊を読破する超多読法」など興味深い内容が紹介されているので、もし興味がありましたらぜひ読んでみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました。